なぜ私が勤めていた会社では、ここ数年で精神的に不調をきたす社員が増えていたのか?
私は精神科医ではありませんが、あの環境に身を置いていたひとりとして、組織内で何が起きていたのか、自分なりの視点で振り返ってみようと思います。
利益第一主義がもたらす「うつ病多発」の背景とは?
民間企業において利益追求が重視されるのは当然のことです。しかし、この「利益第一主義」が、実は心の健康をむしばむ構造を作っているという側面があります。
利益が最優先されるため、業績が振るわなければ、責任を取らされるのは管理職層です。降格や左遷といった処分を目の当たりにした管理職たちは、「次は自分かもしれない」と不安に苛まれます。
その結果、余裕を失い、保守的になり、部下に対して適切なマネジメントができなくなる。こうした状態が連鎖的に生まれていくのです。
リーダー不在の現場と、その背景にある「構造の圧」
経営陣から理不尽とも感じられる業務が下りてきた場合でも、「それはできません」と声を上げることが難しいのが実情です。結果として、そのままの形で部下に伝達され、「これは会社の方針だから、何とか対策を考えてほしい」と依頼せざるを得ない場面も見られました。
その内容が現場の状況と乖離していた場合、部下は「なぜこの仕事を自分が?」と戸惑い、不信感を抱いてしまうことがあります。けれど部下は、上司と対立することで自分の立場が不利になるのを恐れ、感情を飲み込んで黙々とこなしてしまう──この繰り返しです。
もしそんな状況の中でも、「不明点はすべて私に集約してくれ」とリーダーシップを発揮できる上司がいれば、状況は多少なりとも改善されたかもしれません。
しかし、私が勤めていた会社では、そうした行動を自ら進んで取れる上司はほとんど見当たりませんでした。とはいえ、私は彼ら一人ひとりが冷酷だったとは思っていません。むしろ、個人としては温厚で部下想いの人も多かったと思います。
ただ、「組織の中での立場」や「管理職としての保身」、「降格や左遷といった現実的リスク」に縛られていた結果、リーダーシップを発揮できない状況に追い込まれていたのだと思います。
要するに、問題の本質は“人”ではなく、そうせざるを得なくなるような組織構造や資本主義の論理にあると、今では感じています。
なぜ正社員は「休職者」を思いやれないのか?
休職者への気遣いが十分に行き渡らず、どうしても業務の現場では“余裕のなさ”が先行してしまう状況が見受けられました。
急な人員減により、自分の仕事量が一気に増える。そのうえ、代替要員の補充も難しく、ミスをすれば自分の評価に跳ね返ってくる──そんな不安から、「なぜ自分ばかりが負担を背負っているのか」という気持ちになり、無意識のうちにネガティブな感情を抱いてしまうこともあるかもしれません。
さらに、転職すれば年収が下がるかもしれないという不安があるため、多くの人が自分の立場を守ることに精一杯になっています。このように、組織のなかで個々人が“防衛モード”に入り、結果として他者への思いやりが減っていく──それが今の職場の実情ではないでしょうか。
変化には「構造」へのアプローチが必要
このような状況を個人の努力だけで変えるのは難しいと感じています。だからこそ、企業側の働き方改革やマネジメントの見直しといった「構造」そのものへの取り組みが求められていると思います。
今回お話ししたことは、私が実際に経験した一事例にすぎません。しかし、同じような状況に悩んでいる方がいるならば、少しでも共感や気づきに繋がれば幸いです。
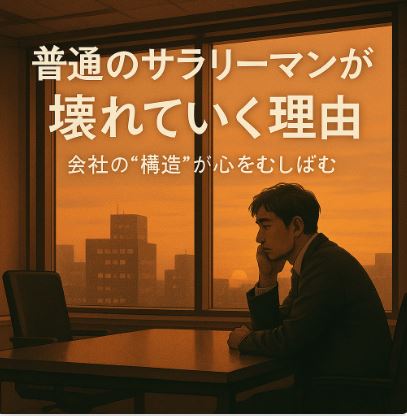


コメント
正社員はかわいそうだと憐みの念を感じるともにその精神力に尊敬の念も感じる。
コメントありがとうございます。正社員は抜け出したくてもローンなどで簡単に抜け出せない状況にハマってしまっていることもありますからね。精神的にタフなように外見からは見えても、本人の中身はボロボロというパターンも多いと思います。