「最近は、ちょっとしたことでメンタルやられる人が増えたよな……」
そんな言葉を耳にすることがあります。
確かに、平成や令和の会社では、うつ病や適応障害での休職は珍しくありません。
私自身、現役時代にそうした同僚や先輩社員、後輩を何人も見てきましたし、自分自身の心がすり減っていたことに気づくまでに、退職してから3年もかかりました。
では、昔のサラリーマンたちはどうだったのでしょうか?
昭和の高度経済成長期——あの時代には、メンタル不調なんて言葉、ほとんど聞かれなかったように思います。
でも、それって「本当にみんな元気だった」のでしょうか。
気になった私は、少し調べてみることにしました。
昭和のサラリーマンにメンタル不調はなかったのか?
まず結論から言えば、あの時代にも「心を病んでいた人」はたくさんいたと思います。
ただ、それが表に出にくかっただけ。
当時は、「男は黙って我慢する」「弱音を吐くのは甘え」という価値観が社会全体に染みついていました。
今のように「うつ病」や「メンタルヘルス」という言葉が一般化していなかった時代です。
精神的に追い詰められても、病院に行くこともなく、上司に相談することもなく、ただひたすらに耐え続ける。
結果、酒に逃げたり、ギャンブルに走ったり、あるいは急に辞めて姿を消す人(失踪)もいたそうです。
それらはすべて、今でいう「心の不調」のサインだったのかもしれません。

見えない不調は、別の形で“噴き出して”いた
昭和の時代には、いわゆる「依存症」と呼ばれるような問題が、今よりも日常的に見られました。
パチンコや競馬といったギャンブルにのめり込み、給料日には財布を空っぽにして帰ってくる人。
家での飲酒が習慣化し、酔って帰宅し家族に暴力を振るう人。
タバコがストレス解消の手段として容認され、1日に2箱以上吸うことが当たり前だった人……。
当時は、こうした行動が「依存症」や「精神的な逃避」として理解されることはほとんどなく、
むしろ「男のストレス発散」「父親のあるある」として片づけられていた節もあります。
けれど今の時代から見れば、それは立派な「心の限界サイン」だったのではないでしょうか。
今はそうした問題行動が減った一方で、代わりに「朝、起き上がれない」「人と話すのがつらい」といった形でメンタルの不調が表面化するようになった。
つまり、心の叫びは時代によって“現れ方”が変わっているだけで、昔も今もサラリーマンという人種は何かしらの形で苦しんでいたのかもしれません。
時代が違うだけで、苦しみの本質は変わらない
思えば、今の時代が特別に“心が弱い人が増えた”というわけではなく、苦しみの「表れ方」が変わっただけではないでしょうか。
昭和は、声を上げにくい時代。
令和は、声を上げやすくなった時代。
職場の風土、SNS、制度、価値観——いろんなものが変わったおかげで、ようやく「心がつらい」と言える土壌ができてきた。
だから、「昔の人は立派だった」「今は甘えてる」ではなく、「どちらの時代も、会社員はしんどかったんだ」と知ることが大切な気がしています。
私がいま思うこと(締めにかえて)
学校では、成人すれば「会社員になること」が当たり前のように教育されます。
資本主義社会の仕組みを考えれば、これはある意味当然の流れかもしれません。
でも、会社員という働き方は——昭和でも平成でも——年齢を重ねるごとに、少しずつ精神をすり減らしていく側面があるのも事実です。
だから私は思うのです。
学生のうちに、「会社員になることで社会を学ぶのは悪くない。でも、それをゴールにしてしまうと、かえって心を蝕むことがある」ということを、もっと早いうちから知っておくべきだと。
社会に出て、会社という場所で人間関係や責任を学ぶのは確かに大事。
でも同時に、「自分はどんなふうに生きていきたいのか?」を節目節目で立ち止まって考える機会も、意識的に持っていくべきだと思うのです。
あくまでも、これは私自身のささやかな私見にすぎません。
けれど、退職して3年経ち、自分の心の変化をじっくり見つめてきた今は、そう強く感じています。

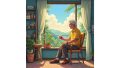

コメント