昭和のサラリーマンは、定年後どうしていたのか?
最近ふと思ったんです。
昭和の時代のサラリーマンって、定年退職した後、どうやって日々を過ごしていたんだろう?
というのも、私自身が早期退職してもう3年。
最初の1〜2か月は、ただただ「何もしない自由」を満喫していたのですが、それも案外すぐに飽きました。
その後はブログを書いたり、YouTubeに挑戦したり、投資の勉強をしてみたり……。
いずれも「収益につながったらラッキー」という軽い気持ちで始めたものですが、気づけば生活の一部になっていました。
でも、ふと立ち止まって考えると、昭和の時代にこんな選択肢ってなかったよなと。
「定年=引退」の時代には、レールがあった
調べてみると、昭和の定年退職後というのは本当に“引退”という言葉が似合う世界でした。
- 55歳で定年退職したら、即年金がもらえる
- 退職金も今より多く、家のローンも完済済み
- 家にいてのんびりテレビ、囲碁・将棋、たまに畑仕事
- パチンコや競馬で時間を潰す人もいた
- 町内会や老人会で地域活動をする人も
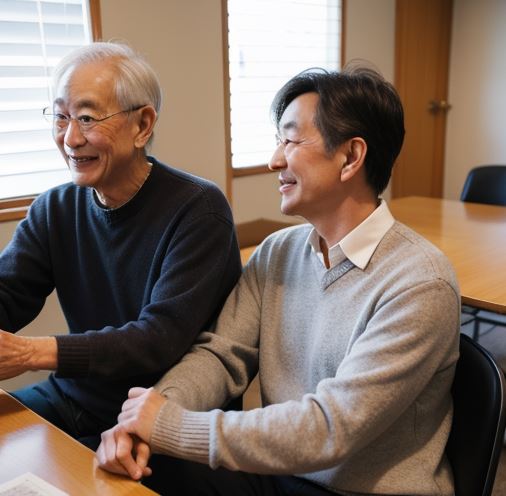
「働かなくても生きていける老後」というレールが、あらかじめ用意されていたんですね。
もちろん、全員が全員そうだったわけではないでしょうけど、「何もしない=当たり前」という空気があったのは事実のようです。
なお、調べたところでは定年が55歳から60歳になったのは1990年から。それ以前は「55歳定年」が一般的で、法律で60歳未満を禁止されたのがこのタイミングでした(←あくまでも素人の私調べです)。
本音では「働きたい」人もいた。でも……
昭和58年(1983年)の調査では、60代男性の約4割が「定年後も何かしら働きたい」と答えていたそうです。
ただ、実際に働いていた人はその半分にも満たなかったようです。
なぜか?
「定年後に働く=生活に困っていると思われる」
「再雇用されてまで働くのは恥ずかしい」
そんな“昭和の空気”があったのかもしれません。
さらに、今のようにタウンワークやバイトル、求人ボックスといった便利なサイトもない。
インターネットが世の中に登場したのが1995年ごろなので、「職業安定所(当時は職安と呼ばれていた)」や「人づて」に頼るしかなかったわけです。
「会社がすべて」だったから、心がぽっかり空いた?
また、これもねっとなどで個人的に調べた情報によれば、昭和の会社員の中には、定年後に精神的な不調を訴える人も少なくなかったようです。
- 部長や課長など役職経験者ほど「自分の居場所がない」と感じやすかった
- 定年後数か月以内に「うつ症状」や「無気力状態」になる人も
- 家にいる夫が増え、妻のストレスが急増したという話も多数
今ほどメンタルヘルスが語られていなかった時代。
仕事を失う=生きがいを失うという側面は、当時の男性にとって想像以上に大きかったのではないかと思います。

令和は自由。でも、そのぶん迷う
今の時代、60歳を過ぎても働く人は増えていて、選択肢も山ほどあります。
- 再雇用・シルバー人材センター
- ネットを活用した副業、投資、情報発信
- フリーランス的な働き方も可能 ・・・・・etc
私自身、外で働くことにはなかなか気が向かなかったものの、
ブログやYouTubeを通じて「個人でできる何か」を見つけていきました。
自由で選べるからこそ、迷うという感覚は今の時代ならではかもしれません。
私の父と、私自身の思い
ちなみに私の父は社員数人の小さな会社で働いており、「定年」という制度はありませんでした。
63歳まで現役で働き、その後体を壊し、66歳で亡くなりました。
だから私は、「定年退職して余生を過ごす元会社員の実の親の姿」を目の前で見たことがありません。
それもあって、昭和の定年後の実態ってどうだったんだろう?と素朴に気になるようになったのかもしれません。
結局、どう生きるかは自分次第(たぶん)
こうしてあれこれ考えてみると、終身雇用だった時代のサラリーマンも、傍から見るほど本人自身は幸福感を感じられていなかったのかも、とも思います。
レールが敷かれていた時代には、そのぶんの“縛り”もあったし、
自由に選べる時代には、そのぶんの“迷い”もある。
結局、リタイア後の人生をどう過ごすかを左右するのは、自分の行動や考え方次第。
そう思います(あくまで私見ですが)。
誰かに決めてもらうんじゃなく、自分で小さな一歩を踏み出す。
そんなリタイア後の過ごし方が、いちばん自然で、長く続くのかもしれません。
※本記事で紹介している「昭和の定年後の実態」については、あくまでも私がネット等で調べた範囲の情報に基づいています。専門家の視点というよりも、私自身の関心と素朴な疑問をもとに書いた一例として読んでいただければ幸いです。

📘 関連書籍のご紹介
この記事のテーマに関連して、ネットなどで調べた中から「定年後の生き方」に役立ちそうな本を2冊ご紹介します。
私自身はまだどちらも未読ですが、昭和と令和のリタイア生活の違いや、退職後の「生きがいの見つけ方」に関心がある方には、参考になるかもしれません。
『定年後からはじまる 生きがいの創造』(太田哲二 編著/2021年)
ポジティブ心理学の視点から、定年後の時間の使い方や自己実現、夫婦関係の再構築などを広く考察した一冊。「ただ暇をつぶす老後」ではなく、「自分らしく生きる人生後半戦」をどうデザインするかがテーマです。
『定年後のかしこい人生設計』(中桐啓貴・三笠書房)
定年後に待ち受ける経済・健康・人間関係の課題を広く扱いながら、喪失感との向き合い方や再スタートのヒントをまとめた一冊。年金や副業などの現実的な情報も織り交ぜられています。
※いずれも私自身がネット情報をもとに内容をまとめたもので、実際の内容や構成はリンク先でご確認ください。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3037e5a7.77fd964e.3037e5a8.7a147386/?me_id=1213310&item_id=20432185&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8061%2F9784382158061_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/465e6fc4.df1b3eab.465e6fc5.b2d95969/?me_id=1309253&item_id=14732556&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooksupply%2Fcabinet%2F04216212%2F560%2F9784837925668.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント
ブログの更新ありがとうございます。
私は現在56歳ですので、昔であれば、もう年金を貰えていたということですね。今、年金を貰えていたとしたら、気分的にも全然違うと思います。そう考えると、65歳支給の現在の制度は過酷ですね。
体力的な個人差はありますが、リタイアした今では、自分が65歳まで、元気に働ける自信がありません。お陰さまで、先日受けた人間ドックでは、特に指摘事項はなかったのですが、やる気というか意欲というのが、年々落ちているのを感じます。いわゆる男性の更年期障害のようなものですね。災害級の暑さの中、働いている同じ年代の人達には感心します。今日なんて津波警報の件で、朝から大変ですよね。
それはそれなりになってしまうのは仕方ないと思いますが。
ひまやりさんが仰るように、どう生きるかはその人次第ですからね。
コメントありがとうございます。
昔のサラリーマンとの違いをあれこれ考えていると、昔は今と違って定年は55歳。
ただし、現役の会社員は週休2日ではなく、週休1日だった(しかも残業は当たり前)ならば、生涯の労働時間の総合計は今と昔とどっちが多いのかな?なんてことも考えます。
ちなみに週休1日ってゾッとします・・・(笑)。
ストレスを抜くヒマもないですね。
確かに週休1日はゾッとします。
私が入社したときは4週6休で、すぐに完全週休2日になりました。高校までは土曜日も昼まで授業がありましたね。
祝日も今よりは少なかったでしょう。
時間だけみると確かにタイトでしたね。
昔は休みが少ない分、給料は毎年「物価上昇分」として上がっていたとも聞いたことがあります。
ただ、いくらお金を稼いでも休みが少ないと娯楽に使える「時間」がなかったと想像します。
恐らく会社員は皆、心休める時間も少なくて年中せかせかしていたのではないでしょうか?