早期退職制度に応募して会社を去った直後、私は“再就職支援会社”を利用しました。
利用理由は、退職前の会社が費用を全額負担してくれたこと、そして何より長年の会社員生活を経て「会社を離れたら何をしていいかわからない」という不安があったからです。
また、同時期に退職した社員の一定数が当然のように登録していたことも要因の1つとなりました。
ですが――。
時間が経った今、あえて言いたいことがあります。
再就職支援会社は、時間と労力の“割に合わない”場所だったということです。
「支援」とは名ばかりの“案内人”
私の担当者は丁寧な方ではありました。
しかし、彼らが持っている再就職先の情報というのは、決して“非公開の優良案件”ではなかったのです。
一度、私はこんなことがありました。
「こんな仕事があります」と手渡された案件が、
なんと私自身が副業で利用していたクラウドワークスで見かけたものだったのです。
つまり、再就職支援会社というのは、
独自の就職ルートや非公開案件を持っているわけではなく、
“探し方”を教える場所にすぎないと感じました。
「それなら、自分で求人サイトを見たほうが早い」――心の中でそう呟いたのを覚えています。
再就職支援会社の“使える”部分もある
とはいえ、再就職支援会社にも使いようによっては役立つ面もあるのは事実です。
たとえば以下のようなメリットは、実際に感じたものです。
① 履歴書・職務経歴書の添削・指導
会社員を長年続けていた人ほど、履歴書なんて学生の頃以来書いていないという人が多いはず。
私もフォーマットや書き方、職務経歴の表現など忘れている部分が多く、そうした点を実務的にサポートしてもらえるのはありがたかったです。
② 面談・セミナーが「失業保険の就職活動実績」にカウントされる
これは意外と大きいメリットです。
再就職支援会社との月1~2回の面談が、ハローワークの「月2回の求職活動実績」にカウントされるのです。
しかも最近はZoomでの面談やオンラインセミナーでもOK。
私自身、担当者との進捗確認だけでカウントされたこともあり、かなり楽に条件を満たせました。
また、支援会社が開催するセミナー(私の場合はZoom参加型の「独立支援セミナー」)も、1回の参加で就職活動1回分としてカウントされます。
私が受けたものは月2回の8回シリーズだったので、4か月間分の実績作りが“ほぼ自動的に”済んだのはありがたかったですね。
「精一杯支援します」の裏にある、支援する側の“本音”
これは私の私見ですが、支援会社の担当者たちにも“事情”があると思っています。
というのも、彼らも私が長年やってきたのと同じ雇われの会社員。
言い方は悪いですが、支援会社の仕組みは“立ち食いそば屋”に近い回転率重視の構造。
一人の利用者が長く居座るほど手間がかかり、業務量が増えるわけです。
となると、やはり「一刻も早く再就職先が決まって“卒業”してくれるとありがたい」というのが、現場の本音ではないかと感じてしまいます。
もちろん表面上は「全力で寄り添います」と言ってくれますが、それもサラリーマンとしての“演技力”込みの仕事なのかもしれません。
かつて自分も同じような“雇われる側”だったからこそ、
「そのフリが仕事になる世界」という構造が、透けて見えてしまう。
これは、長年会社員をしてきたことの功罪かもしれません(笑)・・・。
企業は高額な費用を払って、結局“丸投げ”していないか?
再就職支援会社という仕組みは、一般的に退職者1人あたり数十万円〜100万円近くの費用が、企業側から支払われていると言われています。
でも、冷静に考えてみてください。
ここまでの話で、その金額に見合うサポートだったか?
私は、そうは思えません。
支援会社のおかげで「第2の会社員人生が充実し、60歳まで勤め上げました」
そんな記事も、ブログも、YouTubeも、今まで一度も見たことがありません。
企業はこの現実を分かっているのか?
おそらく分かっている。でもこう言うでしょう。
「退職後に困らないように、ちゃんと支援先はご紹介しましたよ」と。
これが、これからの日本の“制度疲労”の象徴でないとしたら、何なのでしょうか。
【結論】再就職支援会社は、「うまく使えば便利、でも過信すべきではない」
履歴書添削や失業保険の実績づくりなど、形式的に役立つ面はある。
けれど「自分の進路を見つけたい」とか「人生の軸を再構築したい」といった期待を抱いて行くと、がっかりする可能性が高い。
企業も、支援会社も、“整っているように見せる”構造の中で動いている。
だからこそ、最後に自分の未来を決めるのは自分自身しかいない。
再就職支援会社を「使う」のはいい。
でも、「頼る」と、人生の大事な時間を、制度の空洞に吸い取られるだけ――
それが、私がこの数年を経て出した正直な結論です。

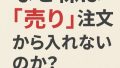

コメント