また早期退職8,000人超──辞めた後の現実は「自己責任」で済ませてよいのか?
2025年もまた、希望退職・早期退職の波が大手企業を中心に広がっています。ヤフーニュースにも掲載された通り、今年1~5月だけで8,700人超。しかもその多くは、まだ黒字経営の企業による「戦略的な人員整理」です。

退職する人々の多くは中高年。職場を離れることで一定の自由や退職金を得る一方、「この先の人生をどう生きるか」という大きな不安を抱えていくことになります。しかし、この記事ではそうした個人の苦悩には一切触れられていません。
退職後に待つ「経済・精神・社会的孤立」の三重苦
私自身、退職後の人生設計に悩む人々の声を数多く耳にしてきました。
私個人も当ブログで書いてきた通り、様々な問題を感じています。
・退職金だけでは老後資金が足りないと気づく
・次の職場が見つからず、孤独や無力感に苦しむ
・社会とのつながりが急に断たれ、孤立する
これらは一過性の問題ではなく、「構造的な社会問題」です。かつては終身雇用のもとで“現役を終えたら静かに余生を過ごす”というモデルが通用しました。しかし、今は平均寿命が延び、60歳以降も20年以上働かねばならない時代です。
「働きたくても、しんどい仕事しかない」──介護、タクシー…そこしかないのか?
多くの中高年退職者に用意される再就職先は、肉体的・精神的にハードな業界が多いです。
例)
・介護職:人手不足を理由に未経験者でも歓迎されるが、実際の現場は過酷
・タクシー:自由度はあるが、長時間労働と歩合制のプレッシャー
これでは、せっかく人生の次章に踏み出した人たちが再び心身をすり減らすだけ。割増退職金を少しずつ切り崩しながら「もう働けない」と感じてしまうケースも少なくありません。
国が本気で向き合うべきは、「退職後の働き方の選択肢」
社会全体として、そろそろ認めるべきです。「人生100年時代」ならば、退職後に安心して第二の人生を設計できる支援体制が必要です。
例えば以下のような政策が検討されるべきです:
・週2~3日の短時間勤務で生活が成り立つ仕組み
・ 中高年向けのキャリア再教育・学び直し支援
・ 在宅・リモートワーク型の公的就労モデル
・ 退職金補填型の給付金 or セーフティベーシックインカム
いずれも「楽して暮らしたい」という話ではありません。健康を維持し、無理せず社会と関われる働き方を実現するための制度設計が急務なのです。
構造改革の裏で、切り捨てられる人を見逃すな
パナソニック、日産、ジャパンディスプレイ──名前を聞けば誰もが知る一流企業が、次々と「構造改革」の名のもとに人を減らしています。これは企業の経営判断として否定されるものではありません。
しかしその裏で、「辞めた人の人生」が制度的に置き去りにされていることを、私たちはもっと問題視すべきです。「構造改革」には、社会的セーフティネットの整備がセットであるべきなのです。
第二の人生を「不安」ではなく「希望」に変えるために
早期退職や希望退職は、企業と働く人との契約終了であると同時に、「人生の再スタート地点」でもあります。
この出発点を不安と孤立で満たすのではなく、希望と選択肢にあふれた社会に変えていくこと。
それは、今この国に生きる私たち一人ひとりと、政策を担う人たちの共通責任ではないでしょうか。
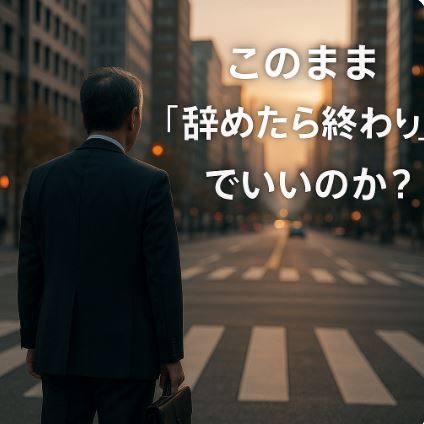
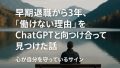

コメント